
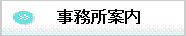

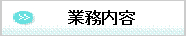



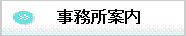

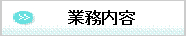


|
◇休眠担保権の抹消 ◇遺産分割のやり直し ◇根抵当権の変更(相続) ◇錯誤による更正(商登) ◇利益相反取引について ◇自己株式の取得について ◇根抵当権の変更(相続) ◇生前贈与(配偶者控除) ◇生前贈与について ◇遺言書について ◇役員の任期について ◇共有地の分筆について |
◇遺言書について 最近は、遺言書を作成するための本が多く市販されており、ご自身で遺言書を作成されている方が多いようです。 遺品を整理していると書斎から遺言書が出てきた、自筆証書遺言なのですが、これが無効な遺言書になっている場合があります。 例えば、○年○月吉日となっている場合です。 ところで、自筆証書遺言の場合、家庭裁判所に行って検認手続きをしなければならず、 この家庭裁判所による検認終了証明が付いていないと、法務局では遺言による登記を受け付けてくれないのですが、 この検認手続きにはかなりの時間がかかります。 検認の申立書を提出してから検認手続きの日までの待ち期間が2か月近くかかることもあります。 (公正証書遺言の場合、検認手続きは不要です。) そして、上記の無効な遺言書であっても、裁判所は、検認終了証明を付けてくれます。 しかし、それでも無効な遺言書であることに変わりはないので、結局、待ったあげくにその遺言書が使えず、 遺産分割協議書を作成して相続登記をすることになってしまいます。 円満な家族であれば、亡き父の遺言どおりに遺産分割しようということになりますが、 そうでなければ、遺言どおりの遺産分割にならず、もめることもあるかと思います。 (私の経験では前者の方だったのでスムーズにいきましたが…) また、市販の本を開くと「相続させる」や「遺贈する」の文言が記載されていますが、 おそらくこの違いを意識せずに「遺贈する」の方を使ったのではないかと思われる遺言書を見たことがあります。 「相続させる」と「遺贈する」では、登記原因が異なり、申請構造(単独申請/共同申請)も異なりますので、添付書類も異なってきます。 (「相続」では原則不要な権利証も「遺贈」では必要となります。その他、「相続」では不要な印鑑証明書も「遺贈」では必要となるなど。) さらに、「遺贈」では、場合により、前提としての住所変更登記が必要になることもあります。 上記の他に、不動産を特定するための記載方法など、注意すべき点があります。 何でも自分でやってみるというのはよいことだと思いますが、相続人にとって複雑な手続きを残さないためにも、 ご自身で作成した遺言書を一度司法書士に見てもらうというのも一つの方法であるかと思います。 |